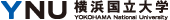PUBLICとは何か —ソウルSVを終えて—
ソウルで滞在した1週間とその後の日本での生活の中で、多様な人々の生活の集合としての都市を考えるときに不可欠な “public” とはどういうことかについて興味が湧いた。
ここでは、考えるきっかけとなった事例の1つである京義線共有地と、その京義線共有地が占拠された背景である韓国の住居権運動の歴史、共有地のパブリックスペースとコモンズの違いについてまとめ、本当の公共性とは何なのかを考えてみたい。
韓国の住居権運動の歴史
1953年、朝鮮戦争終了後、経済発展を短期間で進めるために、韓国は1987年まで独裁政権が続いた。戦争が終結し人口が急激に増加したために、住居基盤の確保が急がれたが、当時ソウル市内にも未だ数十万のバラックが残る厳しい状況だった。そこで当時の独裁政権は、バラックを強制撤去し、マンションやアパートを建てる再開発を行った。しかし、強制撤去されたバラックに住んでいた貧困層は、突然家を失うことになり、冬が厳しいソウルでは、家無しで生きていくのは難しかった。そういった人々の強制撤去に反対する運動が、住居権運動である。60年代、70年代は追い出された人々による10万人規模のデモがあり、80年代からはデモが組織化され、さらに住居権以外の議会、労働運動と連合化するようになった。
1987年、大規模なデモによって独裁政権が倒れると、憲法が改正され、議会制民主主義が採り入れられた。それは政治だけでなく、開発にも採り入れられたことで、協力を通じた新しい住居権運動(制度改善型運動)も生まれた。
しかし、強制撤去の危険は急を要するのに対して、制度改善型運動は実現に時間がかかるため、バリケードや不法占拠で直接抵抗する撤去民運動と2つに運動が分岐した。以来、別々の方法でバラバラに住居権運動を進めてきた。京義線共有地は、今まで公権力によって追い出されてきた撤去民たちの居場所として、2つの運動が協力した新しい住居権運動のタイプである。
京義線共有地
京義線とは、植民地時代に物資輸送のためにソウルから満州までを結んだ鉄道のことである。朝鮮戦争後、国家が南北で分断されたため路線も分断され、現在はソウルからパジュ市までを結んでいる。2000年に地下化されると、その跡地の活用方法が問題になった。
跡地である国有地の活用方法として、弘大入口(ホンデイック)駅から加佐(カジャ)駅までの約1kmは「京義線森の道 (スッキル)」という公園として整備され、そのほかの土地は民間に賃借することで地下化費用等を回収する計画だった。
しかし、“森の道”ができたことでジェントリフィケーションが起こり、周辺の地価は3〜4倍上昇した。ソウル市内の都市再開発が行われている他の地区と同様に、もともと周辺に住んでいた貧困層は地価の上昇によって住み続けられなくなってしまった。
以前から “住居権運動” を続けていた運動家たちは、民間に賃借された土地の中でも、開発されず事業計画も立てられていなかった土地に目をつけて、その場所を「その空間を切実に必要としている人が使うことのできる共有地」として占拠した。これが京義線共有地である

京義線森の道

ビル郡に挟まれて建つ京義線共有地
住居権運動としての新しい展開
これは不法占拠ではあるが、もともと国有地だった共有地は公共のもので、企業が独占してしまうよりも、都市難民・都市民のための場所にするべきであると運動家たちは考えている。運動家たちは、ここをソウル市の25区の既存区から追い出された人たちのために自治的に運営するという趣旨の “26番目の自治区宣言” を2016年に発表した。
また “元制度改善型運動家たち(現在は公務員として重要な役職についている)” が、撤去民運動の防波堤として機能しているために、自治体による強制撤去などはなく、これが “撤去民運動” と “制度改善型運動” の新しい協力のかたちであると指摘する研究者もいる。
パブリックスペースとコモンズ
ここでは不法占拠された共有地をさらに不法占拠する人も存在する。例えば、もともと展示空間だった場所に、ある日誰かが住みはじめたという。最初は互いに警戒していたが、1ヶ月ほどして礼儀正しく互いに挨拶し、2ヶ月後には共有地の中で自らゴミを拾うなどして、自分の役割を探しはじめたという。
これは、当初運動家たちが、京義線共有地を “パブリックスペース” と説明していたが、今では “コモンズ” として説明していることを端的に表している。
パブリックスペースとは、みんなに解放された場所であるが、管理者の存在が不可欠で、誰かに所有されたスペースがみんなに解放されているスペースである。例えば、“森の道” はパブリックスペースである。ストリート・ミュージシャンの演奏、ベンチで寝ることや、ビールを飲むことは “森の道” の中ではできない。それは近隣のマンションに住む人々の迷惑になるからである。つまり “森の道” は近隣住民の私有財産になりつつあると言える。また、パブリックスペースはつくられる際に、普遍的な価値が重視されるために多様な主体を排除してしまうこと、市民の声よりも国家や政府の規則に従ってしまうことが多く、また完全性と完璧性を確保できるよう設計されるために閉鎖的になり、それ以上何かを加えることが難しくなってしまう。
対して、コモンズとは、みんなに属する場所である。空間は必要とする人が使う機会を持っていて、使うためにコストを支払わなけばならない。明文化されてはいないが、同じ空間を使いたい人がいる場合は空間を必要としている人同士で決め、周囲の同意なしでは6ヶ月以上継続して使用できないというルールが共有地にはある。
またコモンズがつくられる際には、多様な人々がその空間の性格を表すことを可能にすること、開放的で、順次的な開発であることが大事であるとされる。京義線共有地では、仮設に近い、共に作っていける水準で建築をつくることが考えられ、そこでは完璧性よりも仮定性が重視された。
共有地の運動家は、すべてのパブリックスペースがコモンズになる必要はないと考えているが、現実に存在するパブリックスペースよりも、現実に存在するコモンズの方がマシであると考えている。例えば、バス停のベンチが壊れていても普通の人は直さない。それはつまり公共がバス停のベンチを持っているからで、市民が本当に持っている公共資源ではないからではないか。ここでは、公共によって用意されたものとしてベンチがあるのではなく、市民が自ら獲得したものであるべきだと考えられている。
公共とはなにか
これらは公と民を分断した考え方ではないかという意見もある。民の代表としての公を考えるならば、公共と市民は別々の主体ではなく、シームレスに繋がっていて、同じ人の別々の一面である。バス停のベンチが壊れているとしたら、ある市民Aは自身では直さないが、Aが日々支払う税金の集積で雇われた、専門の修理業者が直すのだろう。みんなに必要なものを、みんなが負担することで、みんなで使えるようにする。つまり、みんなで少しずつ所有する。それが公共の本質だと考える。しかし、現実では、みんなの所有に偏りが生じてしまう。その結果、公共の支援は必要とする人すべてに届かないのではないか。
なぜ偏りが生じるのだろうか、それは現在の所有という概念が不十分だからであると考える。果たして、お金を払えば本当に “もの” を所有できるのだろうか。お金はその人の価値を適切に価値化できているだろうか。京義線共有地とコモンズの概念を学んだことは、そうした疑問を与えてくれた。
今はまだ偏った公共に翻弄される人々のために、法の隙間、都市の隙間、理想と現実の隙間に、京義線共有地は存在するのだろう。